弥生時代になると、大陸から農耕や新しい技術などがもたらされました。それに伴ない、生活の様子や使われた土器などに、大きく変化がみられるようになってきました。
土器は壺形土器、台付甕形土器、高坏形土器、甑形土器などの器種がみられます。このうち台付甕形土器は、台の付いた甕形土器で、直接炉にたてられ、米などの煮炊きに使われた、調理用の土器であると考えられています。この土器は、弥生時代から古墳時代の前期にかけてたくさんみられ、ほとんどの住居跡からみつかっています。火にかけられたためか、土器の器面にススのようなものが付着してこともあります。全体的に、ハケのようなもので調整された跡が残ります。口の部分に刻みをもつものもありますが、文様はみられません。
また、同じように調理用の土器として、甑形土器があります。この土器は、底に孔が開けられたもので、熱湯の入った甕形土器のうえにのせ、底の孔から入る蒸気で、米を蒸すことに使われたと考えられています。
甑形土器は弥生時代から古墳時代の前期にかけての集落跡では、わずかにみつかるだけで、まれな土器といえます。小形のものが多く、住居跡に置かれた位置やその状況から、特殊な扱いをされた土器と考えられ、日常的に使われたのではなく、まつりなどの際に使われた土器といわれています。さいたま市内でも、みつかった例は少なく、岩槻区内では、上野遺跡や黒谷七島遺跡からみつかっています。
甑形土器は古墳時代後期になり、住居内にカマドがつくられるようになると、一般化していき、胴が長く、底ていき、胴が長く、底に大きな孔をあけた大型のものがみられるようになります。同じように胴の長い甕形土器とあわせ、カマドで使われたようです。また、胴の左右に把手のつくものもわずかにみられます。

↑甑形土器(上から)

甑形土器(左)と台付甕形
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




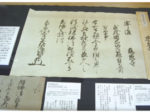








この記事へのコメントはありません。