 「認知症で寝たきりの女性が担ぎ込まれてきました。」
「認知症で寝たきりの女性が担ぎ込まれてきました。」
「犬を連れてきた人が、犬と一緒に体育館に入れてほしいと言ってます。」
「けがをして、足から出血している人が運ばれてきました。」
「知的障害の子どもがいるので、車の中で避難したいという家族がきました。」
「着替えをしたいので、どこかに場所がないかと、女性たちが言っています。」
「電車が止まった旅行中の外国人が避難してきました。全く日本語が通じません。」
「テレビ局が取材に来ました。報道用の駐車場はありますか。インタビューもお願いします。」
これは、さいたま市が実施した「避難所運営の図上訓練」の一場面です。
「地元の避難所の運営を任された」という想定の下で、次々にやってくる避難者の状況や要望を考慮しながら、迅速かつ適切に対応する術を学ぶゲーム形式の訓練です。
さいたま市では、実際に避難所となる現場で行う避難訓練と、区役所の会議室にて行う図上訓練を交互に繰り返しています。
図上訓練では、様々な避難者が想定されています。
乳幼児や妊産婦、高齢者、障害者、外国人、傷病者や遺児なども含まれています。
公平・平等の考え方は大切にしながらも、配慮が必要な方にはどのように対応したらよいのかを限られた時間で考え、話し合うことで今後の災害に備えることができます。
避難所の運営主体は、自治体職員や施設職員(学校教職員や、体育館の指定管理者等)ではなく、あくまで「住民(避難者)が主体である」というのが原則です。
さいたま市では指定避難所ごとに、避難予定の自治会などの地域住民や施設管理者及び避難所担当職員による「避難所運営委員会」を組織しています。
避難予定者の代表として自治会長等が運営リーダー・運営副リーダーになって、地域住民が班員となり、概ね6つの班と施設管理者及び避難所担当職員で構成されています。
つまり、避難してくる住民はお客様ではなく、避難所を運営する主体なのです。
実際の大災害では、停電や断水、トイレが使用禁止になるなど、日常生活からかけ離れたことが次々と起こります。
そんな時、避難所をうまく運営できるかどうかは、自治会のマンパワーにかかっています。
普段から自治会の活動がさかんな地域ほど、災害時に住民が結束して助け合うのを、私は全国の被災地で見てきました。
あなたの自治会は、大丈夫ですか?
【さいたま市防災アドバイザー・加倉井誠】
![]()
![]()
コメント
この記事へのトラックバックはありません。











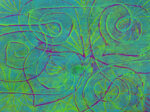

この記事へのコメントはありません。