 子供はどこで、どのように躓く(つまづく)のか。躓きの原因と対応についてお話しします。
子供はどこで、どのように躓く(つまづく)のか。躓きの原因と対応についてお話しします。
子供が何か事を起こす時、自信満々の時もあれば、全く自信が持てない時もあります。
子供が何か事を起こす時、きっとこうなるだろう。
こうあって欲しいと言った期待感が沸き上がります。
また、反対の意識が働くこともあります。
やっても上手く行かないだろう。
やらない方が良いと諦め(あきらめ)てしまう。
この「期待行動」と「諦め行動」が、子供の躓き(つまづき)の原因になります。
これをケースごとに見てみましょう。
第一のケースは、子供が自信に満ちあふれ結果に対する期待を持っており、一般的に子供の行動は生き生きとしています。
この場合、多少の躓きがあっても子どもは自身の力で解決します。
保護者は見守るだけで良いでしょう。
第二のケースです。子供は自信を持っているが、結果に対する期待が持てず、一般的に子供は、不平とか不満が多い。
さらにひどくなると、子供はこうした状況から逃げ出そうとします。
「逃避行動」です。この場合のつまずきに対しては、保護者の積極的対応が望まれます。
「褒める。励ます。子供の言い分をよく聞く」この3原則を徹底することです。
第三のケースですが、結果に対する期待は持てるが子供は自信を失っており、外見では問題がないように見えても、子供の心の奥には「劣等感」が充満しています。
この場合の躓きに対しては、自信を持たせることが必要です。
保護者は、子供に具体的な目標をはっきりと示す必要があります。
 こうすればできるとか。
こうすればできるとか。
目の前の課題をはっきりと示してあげることが大切です。
第4のケースです。子供は自信を失っている上に結果に対する期待も持てないでいます。
子供は「無気力感」にさいなまれています。
この場合のつまずきに対しては一刻も早く手を打つ必要があります。
必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
子供のつまづきの原因に応じて保護者の対応は異なると言うことです。
【NPO法人親子ふれあい教育研究所 代表理事 藤野信行】
コメント
この記事へのトラックバックはありません。











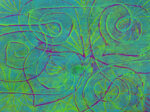

この記事へのコメントはありません。